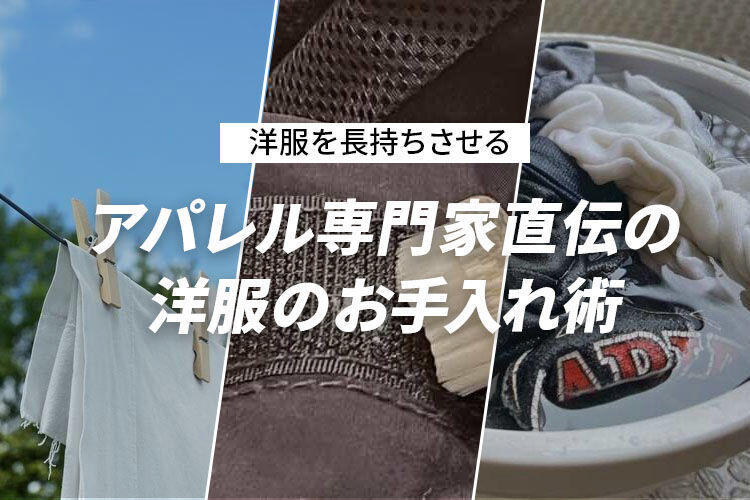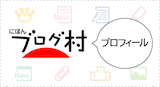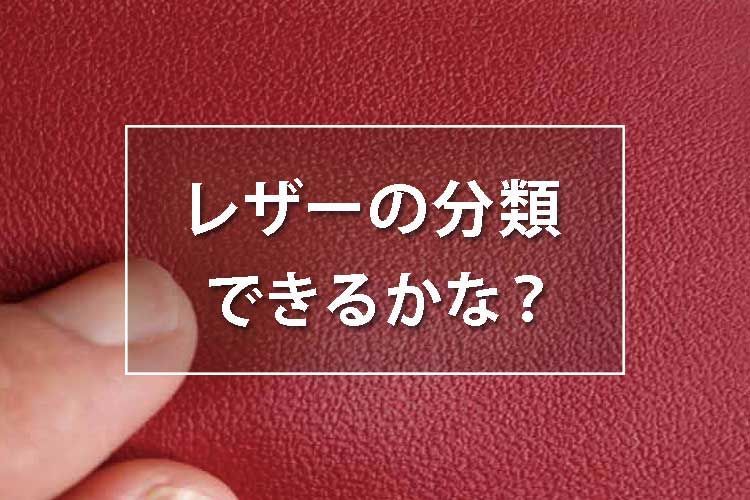
こんにちは。
服の生地についてのブログを書いています、服地パイセンです。
ブログを運営していて記事が増えてくると、人気の記事とそうでもない記事に分かれます。
『全記事ハズレなし』を目標に頑張って書いてはいるのですが、どうしても差は生まれてしまいます。
キーワードの需要が違うので仕方のないことなのですが、年間を通してアクセスの多い記事が、レザーの品質について書いたこのかなり前の記事です。
正直なところ、ぼく自身そこまでレザーに詳しくありません。
ただ、それなりにアパレル業界も長いのである程度は理解していると思います。
最近のレザー関係の話題というと、サステナブルやエシカルの観点から、ヴィーガンレザーやシンセティックレザーが注目されています。
それらの合成皮革や人工皮革は天然の皮革を人工的に模したものです。
つまり、もともとのレザーについて知っているのと知らないのとでは、見え方や感じ方が大きく違ってくるということです。
レザーについて理解しようと思っても、
『種類が多すぎてマニアックすぎる』とハードルが高く感じませんか?
ところが実は、レザーの抑えておくべきポイントって案外少ないんですよ。
ということで、レザーについての基本的な知識を書いてみます。
ところどころ皮革メーカー様から頂いた資料を参考にさしてもらっています。
革の価値観

まず、日本とヨーロッパとでは『皮革』に対する価値観が大きく違うようです。
ヨーロッパでは、長くつかえる丈夫な素材として、皮革がしっかりと生活に根付いています。
例えば祖父が使っていた革製の家具が代々受け継がれたり、長い年月使用したカバンを子どもに託したりと、成熟した皮革文化があります。
日本では代々受け継がれる革のアイテムって何があるのか、僕はちょっと想像できません。
皮と革の違いを知ってますか?

皮革の『かわ』についてですが、『革』と『皮』の違いってなんだと思いますか?
普段意識せずとも、なんとなくで使い分けできていると思いますが、具体的にはどのように表現するのか。
これをわかりやすく説明すると、
皮は動物から剥いで何の加工もされていないもので、革は皮を製品として使えるように加工したものです。
はいだ『皮』はそのままににしておくと硬くなったり腐ったりしてしまいます。
その皮を製品として使用できるようにする作業を『なめし』と呼びます。
このなめし加工を施した物が『革』ですね。
こうして文字で理解すると、頭の整理になると思います。
皮革は表革と裏革がある

革のアイテムでも
スムースレザーは上品な雰囲気、
スエードはカジュアルな雰囲気です。
どちらも同じ皮革ですが、それぞれ印象が全然ちがいます。
何が違うかというと、皮革の表面か裏面かという違いがあります。
スムースレザーに使われるような表側を銀面(ぎんめん)、
スエードのような裏側を床面(とこめん)と呼びます。
スエードが革の裏側だということは、案外知らない人も多いんではないでしょうか。
レザーの動物による分類
レザーはたくさん種類があります。
それこそ覚えようと思ってもイヤになるほどあります。
例えば、
イタリアンスムースレザーとか
ブライドルレザーとか数えあげればキリがありません。
実はそれらは、なめしや加工の種類や生産地が違うので様々な名称がありますが、
もとを辿ると基本的な部分は案外簡単だったりします。
要するに要点さえ抑えておけば、ある程度レザーのことが理解できます。
とりあえず知ってたら十分、という箇所だけまとめます。
使われる動物は案外少ない
天然皮革は文字通り、天然の革です。
動物の皮を利用します。
動物から皮をいただくので、ある程度の大きさがないと十分な量の革が作れません。
そういったこともあり、使われる動物の種類も基本的には限られています。
レザーは年齢や性別で分けられている
例えば同じ牛革でも、『ステア』や『キップ』などの種類があります。
これは、革にする動物の成長段階で分けられています。
成長とともに皮の質感が変わり、革にしたときの特性も変化します。
また性別で呼び方が変わるものもあります。
ここからはどんな動物がレザーに使われているのか??解説していきます。
牛革

『革といったら牛』といっていいほど皮革のメインな素材です。
物量が多いので、他の革と比べると良質な革でも価格が安定していて商品化しやすいという産業上の傾向もあります。
キズの少ない革は面積が少なく希少なので、その分高価になります。
最もポピュラーな牛革ですが、年齢や性別によって下記のように分類されます。
いくつか革の写真を載せていますが、色は染料で変わるので関係ありません。
皮革の表面の質感なんかを見ていただけたらと思います。
ステア(成牛革)

生後3〜6ヶ月に去勢し、2年以上太らせながら育てた雄牛のものです。
厚手で耐久性に優れているので、牛革の中でもっとも多用されます。
厚みが出てくるステアは革小物やバッグに使われることが多いです。
キップ(中牛革)

生後6ヶ月〜2年くらいの牛の革。
カーフよりもやや厚手で、キメの細かさはカーフに次いで上質です。
カウ(成牛革)
生後約2年の雌の革。
キメの細かさと厚みはキップのステアの中間。
ブル(成牛革)
生後3年以上の雌の革。
大型でキメが粗く、丈夫で厚い。
カーフ(子牛革)
生後6ヶ月くらいの仔牛の革。
薄手でキメと繊維構造がもっとも細かく、最上級のレザーとして人気が高いです。
カーフは薄いため、高級革靴に使われることが多いです。
羊革

羊は品種が多く、性状も多様。
毛穴によるキメが細かく、薄くて柔らかいが、相対的にみると革の中では強度に欠けます。
羊革はソフトで肌触りが良いので、手袋や高級レザーウエアに使用されます。
革の中でもシミができやすい、いわゆる敏感肌な方です。
羊革はスエードにすると、非常に柔らかで味があり、高いフィット感を得ることができます。
シープスキン

成羊はシープスキンと呼ばれます。
写真ではわかりづらいのですが、牛革と比べると質感は柔らかいです。
ラムスキン

生後一年以内の子羊はラムスキンと呼ばれます。
シープスキンよりもさらに柔らかく、滑らかな肌触りです。
服に使うと、しなやかな服に仕上がります。
山羊革

繊維が緻密なため、薄くてもある程度丈夫なのが特徴。
表面に乙凸があり、摩擦にも強いです。
ゴート

普通の山羊革はゴートと呼ばれます。
羊革よりも繊維組織が充実しており、強くやや硬めです。
キッド

小山羊の革はキッドと呼ばれます。
ゴートよりもさらに薄くて軽い。発色性にも優れていて染色しやすいという特徴があります。
豚革

豚革は表面に独特な毛穴の模様があり、革としては薄くて軽く、摩擦にも強い。
柔らかい皮を作ることも固く半透明にすることも可能です。
毛穴の形が独特で、その模様をデザインに活かされることもあります。
ちなみに革の中で唯一、日本国内で完全自給することができるのが豚革だそうです。海外へ輸出もしているんだとか。
ピッグ

他の革と比べて、ぽつぽつと毛穴が目立つ質感をしていて、特徴としては通気性に優れています。
靴の内側のライニングを見てみると、豚革が使われていることが多いのは通気性が高いからです。
組織の部位によって差が大きく、おしりの部分が密で硬くなり、均一な柔軟性が得にくいです。
馬革

組織が荒いため、牛に比べると強度は劣りますが、肉厚なものが多いので、結果的に非常に丈夫です。
一般的なホースレザーの他にも、おしりの部分をなめして染色したもので、美しい光沢のコードバンが有名です。
ワイルドなブーツやライダースなどのレザージャケットに使われることが多い。中でもおしりの部分から作られるコードバンは美しい光沢を持ち、メンズの定番アイテムとして使用されます。
コードバン

馬の尻部分を使用したものです。
牛革に比べて繊維が緻密で強度にも優れていて、なめらかな美しい表面
艶やかな光沢がポイントで、使い込むほど味わい深くなる人気のある革です。
鹿革

日本でもかなり昔から革として利用されてきました。
鹿=野生のイメージ通り、ひと昔前は傷が多いので表面を取り除いて使用されることも多かったそうです。
近年は飼育されるので良質な革が増えてきています。
ディアスキン
非常に柔軟で手触りも良く、耐水性に優れていることが特徴。
エキゾチックレザー
上で挙げたような一般的な動物の皮革ではなく、希少な動物からとった皮革のことをエキゾチックレザーといいます。
ヘビやワニ、トカゲなと爬虫類などが多く、哺乳類にはない独特な模様が特徴です。
ワニ

独特のウロコ模様と美しい光沢、圧倒的な存在感を主張するワニの革。
アジア、アフリカ産のクロコダイル、アメリカ産のアリゲーター、養殖のカイマンなど様々な仕上げのものがあります。
ウロコに統一感のある綺麗なものが重宝されています。
キズがついた場合、回復することはないので、取り扱いにも注意が必要です。
ヘビ

小型のものをスネーク、大型のものをパイソンと言います。
種類としてはニシキヘビの革がよく使われます。
革の薄さから様々な染めが施され、そのカラーバリエーションは豊富。
財布やバッグなどに使用されることが多いです。
トカゲ

世界中で3000を越える種類が生息していますが、ワシントン条約上、革製品として使用できるのは極めて少数です。
オーストリッチ

ダチョウ革はオーストリッチと呼ばれ、羽を抜いた跡が最大の特徴です。強靭で重厚さがあり、柔軟性もあり、高級素材としてしられています。
牛革の5〜10倍の強度を持つと言われます。一生ものの高級素材です。
革の加工による分類
ここまで動物の種類をみてきましたが、他にも表面の加工によっても分類されます。
エナメル革

表面に濡れたよえな光沢を持つ、エレガントさが魅力の素材。
銀面(表面)にウレタンなどの光沢の出る樹脂塗料を塗って光沢を出した革。
パテントレザーとも呼ばれ、カーフ、キップ、馬革などが使われることが多いです。
スエード

主に仔牛、山羊、羊などの革からつくられることが多い。革の表面を研磨して起毛させたレザーの一種です。
上でも触れたように、皮革の裏面を使用した、カジュアルな趣の強い素材。
優しい手触りと毛足のしなやかな光沢がポイントで、柔らかなものほど上質なスエードとされます。
ヌバック

スエードと異なり、革の銀面(表面)をバフして仕上げたもの。
スエードと比べると毛足が非常に短く、ビロード状をしています。
ヌバックとスエードの違いは知らなかった人も多いのではないでしょうか。
ヌメ革

成牛や豚の革などを薄いタンニン液でなめし、染色をする前の革。
ベージュまたはかなりうすい茶色をしています。
使い込んでいくと、飴色に経年変化なしていきます。
型押し革
プレスで加熱、加圧して革の銀面に様々な柄を押したもの。

天然のシワと違って、自由に柄の型押しができます。
最後に
動物や加工による皮革の分類を紹介していきました。
これだけわかっていれば、それなりに詳しい方になると思います。
さらに染色やなめしの方法によって、製品の名称は変わってくるので、レザーはとても奥が深い素材です。
冒頭でも書きましたが、もともとのレザーについて知っていると合成皮革の見え方や感じ方が大きく違ってきます。
次回は、そんな合成皮革などについて書いてみようと思います。
そういえばずっと昔、パラブーツの代名詞の『リスレザー』はリスからつくった革だと思っていて、パラブーツ=リスだと思っていました。
リスレザーは油分を多く含んだ牛革をブランディングしたもので、リスから作った革ではありません。
本文でも少し触れましたが、ある程度の大きさがないと皮をつかえないので、リスではないのは当たり前なんですけどね。
誰にも言いませんでしたが、今思うとなんだか恥ずかしいですね。
パラブーツに関しての記事もよかったら読んでみてください。
いつもコメントやはてなブックマークいただきありがとうございます。
とてもありがたく、何よりとても励みになります。
はじめましての方も、思ったことはお気軽にコメントお願いします。
服の生地や環境についてブログを書いているので、よろしければ読者登録お願いします。
↓ブログ村ランキングに参加しています。よろしければ、そちらもチェックしていだけると励みになります。