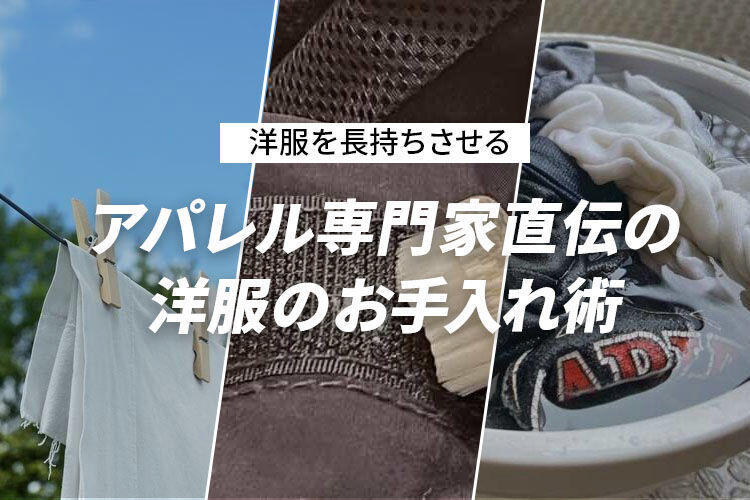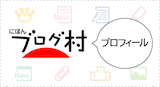こんにちは。 服の生地についてのブログを書いています、服地パイセンです。
服の生地って覚えられないくらいたくさんの種類がありますよね。
皮革や不織布を除いた一般的な服の生地は、大きく分けて織物と編み物があります。
基本的にシャツの生地は織物、Tシャツやニットなんかは編み物です。
前回の記事で服地の分類について書きましたが、今回はそのシャツなんかに使われる生地、織物についてです。
織物について知っていると、これから出会う生地など、さまざまな服地についてあらたな発見があるはずです。
織物(テキスタイル)の三原組織と種類
織物とは、たて糸とよこ糸とを交差させてつくられる布のことです。
シャツやアウター、パンツなど様々なアイテムに使われ、生地の種類はたくさんあります。
しかし、織物を種類毎に分類してみると、たったの3種類しかありません。
3種類なのでタイトルでは御三家という言い方をしましたが、
これらは「織物の三原組織」と呼ばれてます。
①平織り
②綾織り
③朱子(しゅす)織り
今回はこの3つの基本の織り方について、それぞれの特徴と、代表的な生地なんかを紹介していきます。
どんなに変わったように見える織物でも、この三原組織か、もしくは三原組織の変化形になります。
まず、何回か出てくるので「組織点」という単語だけ覚えておいてください。
組織点とは
たて糸とよこ糸が交差して交わっているいる箇所を組織点と言います。
組織点が多いということは、たて糸とよこ糸が多く組み合わさっているので、頑丈であるといえます。
それでは、三原組織を順番にみていきましょう。
平織りとは。織り方は?

たて糸1本とよこ糸1本とが交互に交差した、もっともわかりやすい織組です。
たて糸一本に対してよこ糸一本なので、織物の中では組織点がもっとも多く、地合いがしっかりしている実用的な織物です。
シャツ生地に使われることが多いような気がします。
英語では「プレーン・ウィーヴ」といいます。
平織りの特徴
平織は組織点が多いので、硬く、ハリがあります。
耐久性の高い生地に仕上がることが特徴です。
平織りの生地と種類の例
実際に平織りにはどのような生地があるのか、一例を紹介します。
オックスフォードは平織り

ブルックスブラザーズのボタンダウンシャツに使われたりする生地です。
ふっくらとしているけど、厚ぼったくなく、品の良い光沢感があるのが特徴です。
平織の変化織であるななこ織でつくられます。ななこ織はたて糸とよこ糸を複数本引き揃えて、一本の糸のように扱う織り方です。
オックスフォード(チェック)

同じオックスフォードですが、こちらの方が織り方がわかりやすいですね。
ちなみにオックスフォードはスコットランド生まれで、オックスフォード・シャーティングというのがオリジナルな名称です。
平織のリネン

しっかりとした繊維のリネンは、コシがあり耐久性もあります。
吸水力や発散性に優れた素材なので、汗ばむ季節にぴったり。
キャンバス生地も平織り

ダックや帆布ともいわれます。
帆やトートバッグなんかに使われるような丈夫な生地です。
平織のナイロン

強度の高いナイロンを平織りに織った、軽くて耐久性も高い生地です。タフな使用に耐える丈夫さです。
薄手の春物アウターに使われたりします。
次は綾織りです。
綾織りとは。織り方は?

たて糸がよこ糸2本の上を連続して通り、次いでよこ糸一本の下を通り、次に2本の上を通るような組織です。
綾織は組織点が斜め方向に連続し、布地に斜めの線が現れるのが特徴で、斜文織りともいわれます。
綾織りは英語で「ツイル・ウィーヴ」といいます。
ツイル(綾織り)の特徴
組織の組み方上、生地の強度は平織より若干弱いといわれていますが、その分繊維の太い、厚めの生地を織ることができるから強度は変わらないとか、色々言われています。
いずれにせよ、綾織の生地も丈夫です。
チノもデニムも実は同じ綾織り
意外な気もしますが、デニムとチノの分類は同じ、綾織りになります。
なんか意外じゃないですか?
チノとデニムって全く別物として捉えてしまいがちですが、織り方でいうと同じ分類なんです。
あとでもう少し詳しく書きます。
綾織りの生地の種類と例
そんな綾織りの生地をみていきましょう。
チノクロスはまさにツイル

チノパンなどのカジュアルウェアやワークウェアに使われる生地です。
平織りと違って、斜めの線がはっきり見えますね。
デニムの生地感(60〜70年代)

少し古いリーバイスのデニムの生地です。
下にあるもう少し新しいデニム生地の画像と見比べてみてください。
デニムの生地感②(90年代)

こちらは比較的年代の新しいリーバイスのデニムです。
こうして生地をよく見てみると、古い生地のものは糸の太さが不均等で、新しいものは糸の太さが均等です。
これは糸を均一に撚る技術が進歩したためです。
糸の太さにムラがあり綾目が崩れることで生地の表面に凹凸ができ、風合いが生まれます。
ヴィンテージウェアに独特な風合いがあるのは、不均等な糸のおかげでもあるんです。
フランスのツイル生地(50年代)

もう一つ古い綾織の生地を載せます。
綾織の生地の画像をいくつか載せましたが、よーく見てくれた人は気づいたかも知れません。
綾目が右を向いているもの、左を向いているものがあるということに。
「そんなの服にしたら同じじゃないか」と思うかもしれませんが、実はけっこう違いがあるんです。
どういうことでしょうか。
右綾は耐久性に優れていて左綾は柔軟性がある
まず、生地を構成するための糸はねじってつくられているということを覚えておいてください(例外としてねじらない糸もあります)。
そして基本的に糸の撚りは左撚り(Z撚り)です。

右綾に織ると、左撚りの糸を逆方向に織るせいで力がはいり、目が詰まった状態で織られるそうです。
たとえば、リーバイスのデニムは右綾、リーのデニムは左綾。
右綾の方がゴツゴツした色落ち、左綾の方がサラッとした色落ちになるなんて言われています。
そう思うと、たしかにリーバイスの方が無骨な色落ちをしている気がします。
ちなみに最新のデニムを織る織機は右綾に対応しているので、左綾は大量生産できないと聞いたことがあります。
綾織だけでもとても奥が深いのです。
最後は朱子織りです。
朱子織りとは。織り方は?

朱子織り(しゅすおり)は、たて糸とよこ糸の交差する点をなるべく目立たないようにして、織物の表面に経糸または緯糸を長く浮かせた織り方です。
糸が交差している点が少ない為、糸の密度を高くして、より厚手の生地を織ることもできます。
英語で「サテン・ウィーヴ」といい、その名の通りサテン生地を思い浮かべてみるとわかりやすいと思います。
「サテン」は生地の名前のように使われていますが、実際は朱子織の事を指しています。
朱子織りの特徴
朱子織りで織った織物は、光沢があり高級感のある生地ができあがります。
交差している点を少なくすることで表面の凹凸が少なくなり光沢が生まれます。
糸にシルクなど光沢のある糸を使うと、より光沢感の強い織物になります。
また、糸同士が複雑に絡み合っていないのでドレープ性があり、綺麗に生地が垂れます。
組織点が少ないだけでなく、たて糸またはよこ糸が長く浮いている為、片方の糸だけが表に表れているように見えます。
しかし、平織りや綾織りと比べると糸の浮いている部分が多いので、摩擦などに対する強度が弱く、キズがつきやすいという弱点もあります。
朱子織りの生地の例
朱子織の生地をみていきましょう。
光沢感のあるサテン

光沢感のある、いかにもサテンらしい生地です。
一般的にサテンといえば、まず想像するのがこんなイメージだと思います。
光沢感がないサテンも

カジュアルな朱子織のパンツの生地です。
上のテロテロのサテンと違い、太めの光沢のない糸で織り上げるとこんな雰囲気になります。
ミリタリーウェアでよく使用されるバックサテンは裏朱子織りと言って、サテンの裏面を使った生地になります。
最後に
家にある物を三原組織の分類にあてはめただけなので、これらはほんの一例です。生地はまだまだあって、本当に奥が深いです。
目についた生地をよく見てみてみると面白い発見があるかもしれません。
その他の柄や、 洋服の生地や素材、縫製について解説しているのでよかったら合わせて読んでみてください。
▶︎『生地・素材・縫製』について
感想などをコメントいただけるのが、何よりとても嬉しいです。
はじめましての方も、思ったことはお気軽にコメントお願いします。
服の生地や環境についてブログを書いているので、よろしければ読者登録お願いします。
↓ブログ村ランキングに参加しています。よろしければ、バナーをクリックしていだけると励みになります。